「ことわざ」と「神使像」のコラボ
前門の虎、後門の狼
日常よく使われる、ことわざ・故事成語・慣用句・四字熟語の中には、動物が入っている語句がたくさんあります。これらのうち、「2種類以上の動物が入っている語句」の動物に、「神使像めぐり」で採録した神使(動物)像の写真を当てはめてみました。語句に載るすべての動物をカバーできました。神使になった動物は、日常生活の中でよく知られ親しまれている動物でもあったのです。なお、語句の意味、解釈などもご参考までに載せましたが、「故事ことわざ辞典」(http://kotowaza-allguide.com/)を主に参照、引用させていただきました。
「ことわざ」を「動物像写真」入りでお楽しみください。 ↓目次(クリック)
いずれの写真も、クリックして拡大写真をご覧いただけます。
1 蛙鳴蝉噪(あめいせんそう)
蛙(カエル)や蝉(セミ)がやかましく鳴き騒ぐことから、ただがやがやとしゃべりたてたり、内容が無いくだらない議論や文をいう。
水宮神社(埼玉県富士見市水子) 京都御所(京都市)紫宸殿の蔀戸(しとみど)の蝉の飾り金具
2 意馬心猿(いばしんえん)
乱れ動く心を、奔走する馬と騒ぎ立てる猿にたとえて、心が煩悩や欲望のために抑えがたいこと。
貴船神社(京都市左京区鞍馬貴船町) 日枝神社(埼玉県越谷市相模町)
3 牛は牛連れ、馬は馬連れ(うしはうしづれ、うまはうまづれ)
牛と馬は歩調が合わないが、牛同士や馬同士なら歩調が合い、それぞれにふさわしい連れである。同類や似た者同士は自然と集まりやすく、調和もとれて物事もうまくいく。
満願寺(黒岩虚空蔵)(福島県福島市黒岩) 西宮神社(兵庫県西宮市社家町)
4 牛も千里、馬も千里(うしもせんり、うまもせんり)
足ののろい牛でも、足の速い馬でも、同じ目的地に着くことから、早くても遅くても、上手でも下手でも、行き着く先(結果)は同じだから慌てることはない。
日向薬師「虚空蔵菩薩祠」(神奈川県伊勢原市日向) 落葉城山妙見寺(兵庫県神戸市北区有馬町)
5 烏頭白くして馬角を生ず(うとうしろくしてうまつのをしょうず)
頭の白い烏(カラス)や頭に角の生えた馬はいるはずはない。そのようなありえないと思っていたこと、まさかと思っていたことが実際に起きること。
高根町・熊野権現(千葉県船橋市高根町) 保食神社(青森市鶴ヶ坂)
6 烏兎匆匆(うとそうそう)
中国の伝説では、太陽には三本足の烏(金烏)が棲み、月には兎が棲むとされることから、「烏兎」は歳月(月日)の意に用いられる。「匆匆」は急ぐさま、慌ただしいさまをいう。月日の経つのが慌ただしく早いさま。
羽黒山三神合祭殿(山形県鶴岡市羽黒町手向) 月山本宮(山形県鶴岡市羽黒町手向)
7 鵜の真似をする烏(うのまねをするからす)
鵜(ウ)も烏(カラス)も同じ黒い鳥で姿が似ているが、鵜は潜水が得意で、烏はうまく泳げない。その烏が鵜の真似をして魚を捕ろうとしても、水に溺れるだけということから、自分の能力を省みず、人真似をして失敗すること。
鵜戸神宮(宮崎県日南市)祭壇前の木鼻の鵜 高根町・熊野権現(千葉県船橋市高根町)
8 鵜の目、鷹の目(うのめたかのめ)
鵜や鷹が獲物をねらうときの鋭い目つきや様子から、熱心に物(欠点や欠陥、あら)を探すさま。また、そのときの鋭い目つき。
鵜戸神宮(宮崎県日南市)祭壇前の木鼻の鵜 隼鷹神社(福岡県小郡市横隈)
9 馬に乗るまでは牛に乗れ(うまにのるまではうしにのれ)
馬は牛より速いがいきなり乗りこなすのは難しい。まずは牛で乗り方の訓練をせよとの意。下働き(低い地位)で実力をつけてから高い地位に、最善策が取れないならば、次善の策を取れということ。
荒倉神社(山形県鶴岡市大字西目) 山田天満宮(名古屋市北区)
10 馬を牛に乗り換える(うまをうしにのりかえる)
走るのが速い馬から、歩みの遅い牛に乗り換えることになるの意から、すぐれているほう(良いもの)を捨て、劣っているほう(悪いもの)を採ること。
白山姫神社(青森県黒石市袋) 矢奈比売神社(静岡県磐田市見付)
11 馬を買わんと欲してまず牛を問う(うまをかわんとほっしてまずうしをとう)
馬を高価で相場(値段)のわからない物、牛を身近で値段の見当がつく物として、高価な物や相場のわからない物を買うときには、先ず、身近な物の値段を尋ねて売値が妥当かどうかを判断しなさい。
高田・日吉神社(佐賀県小城市三日月町) 菅原神社(埼玉県東松山市松山)
12 烏鷺の争い(うろのあらそい)
烏(カラス)は羽色が黒く、鷺(サギ)は羽色が白い。これを碁石の黒白に見立てて、「囲碁」をうつことをいう。
高根町・熊野神社(千葉県船橋市高根町) 白鷺神社( 栃木県河内郡上三川町)
13 鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)
「鴛鴦」はおしどりのことで、「鴛」は雄、「鴦」は雌を表し、いつも雄と雌が寄り添って離れない。このことから、夫婦の仲がよいこと。
(左右とも)鴨鴛寺正覚院(千葉県八千代市村上)
14 鬼が出るか蛇が出るか(おにがでるかじゃがでるか)
鬼も蛇も不気味なもののたとえとして、これから先どんな恐ろしいことが起きるか予測がつかないこと。
東霧島神社(宮崎県都城市高崎町) 盛岡八幡宮(岩手県盛岡市八幡町)
15 雁が飛べば石亀も地団駄(かりがとべばいしがめもじだんだ)
雁が飛ぶのを見て、石亀が自分も飛びたいと思ったが飛べず悔しがって地団駄を踏む意。自分の能力を考えないで他人のまねをしたがるたとえ。
東京都三鷹市新川5丁目・仙川沿い 隅田川神社(東京都墨田区堤通)
16 狐と貍の化かしあい(きつねとたぬきのばかしあい)
狐も狸も人を化かすとされていることから、悪賢い者どうしが互いにだまし合うこと。
王子稲荷神社(東京都北区王子) 不空院(I奈良市高畑町)
17 狐を馬に乗せたよう(きつねをうまにのせたよう)
「夕暮れに若い女に化けた狐が馬に乗せてもらうが、ほんの少し乗っただけで狐の姿に戻って走り去った」との話(今昔物語集)から。馬に乗ったこともないあるいは乗るべきでないキツネが馬の背に乗った時のように、落ち着きのない様子。また、言うことがいいかげんで信用できないこと。
小野照崎神社(東京都台東区下谷) 神田神社(神田明神)(東京都千代田区外神田)
18 窮鼠猫を噛む(きゅうそねこをかむ)
追い詰められて逃げ場を失った鼠は猫に噛みつくことがあるとのこと。絶体絶命の窮地に追い詰められれば、弱い者でも強い者に逆襲することがある。また、そこまで追い詰めるなということ。
福相寺(東京都杉並区堀の内) 熊田坂・温泉神社(栃木県那須塩原市黒磯・赤坂)
19 騏驎も老いては駑馬に劣る(きりんもおいてはどばにおとる)
「騏驎」とはすばらしい駿馬のこと(「麒麟」ではない)。「駑馬」とは駄馬のことで転じて平凡な馬・愚かな馬のことをいう。騏驎とよばれたすぐれた名馬でも、年老いると足ののろい駄馬以下になるという意味から、いかにすぐれた人物であっても老いによってその才覚は鈍り、普通の人にも劣るようになるということ。
西宮神社(兵庫県西宮市家町) 保食神社(青森県石黒市境松)
20 群羊を駆って猛虎を攻む(ぐんようをかってもうこをせむ)
一頭では、虎に比べてはるかに弱い羊であっても、群れとして集めて攻めれば、強い虎に立ち向かうことが出来る。弱い者を大勢集めて強い者を攻めること。多くの弱小国を集めて連合し、強国に対抗すること。(また逆に、弱者をいくらたくさん集めて強者に立ち向かわせても勝ち目はないこと、との解釈もあるようです。)
聖天院・勝楽寺(埼玉県日高市新堀) 法輪寺(京都市西京区嵐山)
21 鶏群の一鶴(けいぐんのいっかく)
鶏(ニワトリ)の群れに一羽だけ鶴(ツル)がまじっていることから、多くの凡人の中に、一人だけ抜きん出てすぐれた人がまじっていること。
平群(へぐり)神社(三重県桑名市志知) 伊和神社(兵庫県宍粟市一宮町)
22 鶏口となるも牛後となるなかれ(けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ)
「鶏口」は小さな団体の長を、「牛後」は牛の尻の意味から転じて、大きな団体に使われる者を意味する。大きな集団の中で尻にいて使われるよりも、小さな集団であっても長となるほうがよい。
須賀川牡丹園(福島県須賀川市) 牛島神社(東京都墨田区向島)
23 犬猿の仲(けんえんのなか)
犬と猿は、仲の悪いものの代名詞とされている。非常に仲が悪いことをいう。
泉涌寺即成院(京都市東山区泉涌寺山内町) 大豊神社(京都市左京区鹿ヶ谷)
24 犬馬の労(けんばのろう)
犬や馬が、主人のために忠実に仕えるということから、目上の人、または他人のために全力を尽くすことを、へりくだっていうことば。
城山神明社(千葉県君津市久留里字内山) 皆瀬・八幡宮(五所川原市唐笠柳)
25 狡兎死して走狗烹らる(こうとししてそうくにらる)
「狡兎」とはすばしっこい兎。「走狗」とは猟犬のこと。兎を捕まえる猟犬も、兎が死んでいなくなれば用無しになって煮て食われる、とのことから、価値があるうちは大事にされるが、価値がなくなれば簡単に捨てられることをいう。必要なときは重宝がられるが、用がなくなればあっさり捨てられることのたとえ。
淡海国玉神社(静岡県磐田市見付) 成田山新勝寺表参道(千葉県成田市成田)
26 鷺を烏と言いくるめる(さぎをからすといいくるめる)
白い鷺(サギ)であることは一目瞭然なのに、黒い烏(カラス)だと言い張ることから、明らかに正しくないのに、ものの道理を強引に言い曲げることのたとえ。
白鷺神社( 栃木県河内郡上三川町) 高根町・熊野神社(千葉県船橋市高根町)
27 鹿を指して馬と為す(しかをさしてうまとなす)
「史記・秦始皇本紀」にある故事に基づく。秦の始皇帝が死んだ後、悪臣の趙高が自分の権勢を試そうとして、鹿を馬であるといつわって二世皇帝に鹿を献上した。趙高を恐れてほとんどの者は異議を唱えなかったが、「あれは鹿だ」と言った者は処刑された。理屈に合わないことや間違いを権力で威圧して無理に押し通すこと。
春日神社(静岡県浜松市笠井町) 金毘羅宮(香川県仲多度郡琴平町)
28 前門の虎、後門の狼(ぜんもんのとら、こうもんのおおかみ)
「表門で虎の侵入を防いでいるときに、裏門からは狼(オオカミ)が侵入してくる、すなわち、前後から、虎と狼に挟み撃ちされる状況」の中国の故事から、一つの災難を逃れても、またもう一つの災難が襲ってくること、また、進退窮まった状況。
天現寺(東京都港区南麻布) 大田原神社(杤木県大田原市山の手2)
29 鶴は千年、亀は万年(つるはせんねん、かめはまんねん)
鶴と亀は寿命が長い代表とされて目出度いものとされることから、長寿や縁起を祝うときのことばとして用いられる。実際の寿命は、鶴(タンチョウヅル)が20~30年、亀(ゾウガメ)は100~200年といわれている。
物部神社(島根県大田市川合町) 松尾大社(京都市西京区)
30 鳶が鷹を生む(とびがたかをうむ)
鳶(トビ)も鷹(タカ)も同じ仲間で、姿や大きさも似ているが、鳶を平凡なものとし、鷹をすぐれたものにたとえて、平凡な親からすぐれた子供が生まれること。
月隈・八幡神社(福岡県福岡市博多区月隈) 隼鷹(じゅんよう)神社(福岡県小郡市横隈)
31 虎の威を借る狐(とらのいをかるきつね)
虎に食われそうになった狐が、「私は百獣の王である。私について来い」というので、虎が狐の後をついていくと獣たちはみな逃げだしていく。虎は獣たちが自分を恐れて逃げたことに気づかず、狐を見て逃げ出したと思い込んだ。この話から、権勢を持つ者に頼って、威張る小者のこと。
箭弓稲荷神社(埼玉県東松山市箭弓町) 鞍馬寺(京都市左京区鞍馬本町)
32 鳴く猫は鼠を捕らぬ(なくねこはねずみをとらぬ)
よく鳴く猫はあまり鼠を捕らず、鼠を捕る猫は鳴かないことから、おしゃべりな者は、口先だけで実行力がないこと。
木嶋神社(金毘羅神社内-京都府丹後市峰山町) 大豊神社(京都市左京区鹿ヶ谷)
33 羊の皮を被った(着た)狼
羊は大人しく従順な弱者、狼は乱暴な狼藉者とされることから、親切そうにふるまっているが、内心ではよからぬことを考えている人物のたとえ。一見 礼儀正しく親切そうな人を装っているが、じつは腹黒い策略家。
瑞円寺(東京都渋谷区千駄ヶ谷) 三峯神社(埼玉県秩父市)
34 風する馬牛も相及ばず(ふうするばぎゅうもあいおよばず)
「風する」は発情した獣の雌雄が互いに相手を求める意。求め合う雌雄でさえ会えないほど遠く離れていること。自分とはまったく関係がないこと。また、そういう態度をとること。
阿部野神社(大阪府大阪市阿倍野区北畠) 山田天満宮(名古屋市北区山田町)
35 豚に念仏猫に経(ぶたにねんぶつねこにきょう)
豚に念仏を唱えても、猫に経を聞かせても、ありがたみが理解できない。どんなに立派な教えも、それを理解できない者に言い聞かせたところで、何の意味もなさないこと。
武蔵御嶽神社(東京都青梅市御嶽山) 修那羅峠・安宮神社(長野県筑北村真田)
36 蛇が蛙を呑んだよう(へびがかえるをのんだよう)
蛇が蛙を呑み込んだときのさまから、細長い物の途中がふくれあがって、格好が悪いことのたとえ。
成田山新勝寺表参道(千葉県成田市成田) 延命寺(東京都青梅市住江町)
37 蛇に睨まれた蛙(へびににらまれたかえる)
蛇に睨まれた蛙が、恐ろしくて身動きできなくなる様子から、非常に恐ろしいものや強いもの、苦手なものの前では、身がすくんで動けなくなるようす。
姥宮神社(埼玉県寄居町風布 ) 白蛇弁財天(栃木県真岡市久下田)
38 封豕長蛇(ほうしちょうだ)
「封豕」とは大きい豚・猪のこと。巨大ないのししは何でも食べ貪欲、長い蛇は物を丸飲みして残酷である。貪欲で残酷な国、人、またはその行いをいう。
禅居庵(京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町) 光福院弁財天堂(埼玉県三郷市早稲田)
39 学ぶ者は牛毛の如く、成る者は麟角ご如しとし(まなぶものはぎゅうもうのごとくなるものはりんかくのごとし)
学問を志す者は牛の毛のように大勢いるが、学問を究めることができる者は麒麟の角のようにまれである。
北野天神(牛天神)(東京都文京区春日一丁目) 西本願寺唐門(京都市下京区堀川通花屋町下ル)
40 焼け野の雉子、夜の鶴(やけののきぎす、よるのつる)
「きぎす」はキジ(雉)の古名。雉は巣のある野を焼かれたら、自分の危険もかえりみず子を救おうとし、鶴は霜の降りる寒い夜に翼で子をおおって暖めるとのことから、子を思う親の情愛が深いことのたとえ。
大谷場・氷川神社(埼玉県さいたま市南区南本町) 春清寺(東京都三鷹市新川4丁目)
41 羊質虎皮(ようしつこひ)
実際は羊なのに、虎の皮をかぶっているの意味から、外見だけは立派だが、それに実質が伴っていないこと。
野仏庵(京都市左京区一条寺葉山町) 多門院毘沙門堂(埼玉県所沢市中富)
42 羊頭狗肉(ようとうくにく)
「狗肉」とは、犬の肉のこと。羊の頭を看板に掲げながら、実際には犬の肉を売ってごまかすことから、見かけと実質がともなわないことのたとえ。立派なものをおとりに使い、実際は粗悪なものを売ることのたとえ。
早稲田大学図書館通用口(東京都新宿区西早稲田) 高龗(タカオ)神社(栃木県宇都宮市河内町立伏)
43 欲の熊鷹股裂くる(よくのくまたかまたさくる)
熊鷹が二頭の猪をつかんだところ、猪は驚いて左右に分かれて逃げ出した。鷹は逃がすまいとどちらも放さなかったったので、股が裂けて死んでしまった。あまりに欲が深いと、自分の身に災いをもたらすというたとえ
隼鷹神社(福岡県小郡市横隈) 建仁寺禅居庵(京都市東山区大和大路通四条下ル)
44 竜虎相搏つ(りゅうこあいうつ)
竜と虎は、強い動物の双璧とされ力量が互角で優劣つけ難いことから、すぐれた実力を持つ英雄や強豪同士が勝敗を争うこと。
養沢神社(東京都あきるの市上養沢) 神楽坂善国寺(東京都新宿区神楽坂)
45 竜頭蛇尾(りゅうとうだび)
頭は竜のように立派で、尾は蛇のしっぽのように尻すぼみになることから、はじめは勢いが盛んだが、終わりはふるわないこと。
大山阿夫利神社「二重社」(神奈川県伊勢原市大山) 矢川弁財天(東京都立川市羽衣町)
46 鯉の滝登り(こいのたきのぼり)
黄河上流にある竜門の滝と呼ばれる急流を登りきれた鯉は、化して竜になるという中国の伝説に基づき、目覚ましく立身出世すること。
栗橋町・八坂神社(埼玉県栗橋町北) 養沢神社(東京都あきるの市上養沢)
47 猿に烏帽子(さるにえぼし)
「烏帽子」は、成人男性が礼服を着用する際にかぶった帽子。帽子を猿にかぶせても、そぐわないことから、似つかわしくないことをするたとえ。また、外見だけを取り繕って、中身が伴わないこと。
左から 東金日吉神社(千葉県東金市大豆谷) 津知日吉神社(兵庫県芦屋市津知町) 猿丸神社(京都府綴喜群宇治田原町) 江戸山王日枝神社(東京都千代田区永田町)
48 猫に小判(ねこにこばん)
猫は鰹節には飛びつくが小判の価値はわからない。価値の分からない人に貴重なものを与えても何の役にも立たないこと。
左から 自性院(東京都新宿区西落合) 神楽坂善国寺(東京都新宿区神楽坂)毘沙門天のムカデ小判 観泉寺(東京都杉並区今川)
49 二兎を追う者は一兎をも得ず(にとをおうものはいっともえず)
二羽の兎を同時に捕まえようとする者は、結局は一羽も捕まえられないということから、欲を出して同時に二つのことをうまくやろうとすると、結局はどちらも失敗すること。一つの物事に集中せずあちらこちらに気を取られることへの戒め。
岡崎神社(京都市左京区岡崎天王町)
縁結び祈願 —- 撫でるのは、左右2兎の像ではなく片方の像(1兎)だけのほうがいいのでは!左右-1024x420.jpg)
50 張子の虎(はりこのとら)
張り子の虎は、虎の姿容を紙を貼り重ねて(張り子で)造ったもので、中は空洞で首が振り動く仕組みの郷土玩具。弱いくせに虚勢を張る見掛け倒しの人(空威張りをする人)や、何にでも頷く主体性のない人のたとえ。
信貴山朝護孫子寺(奈良県生駒郡j平群町)
51 鰻上り(うなぎのぼり)
うなぎ(鰻)は川を遡(さかのぼ)るが、その上る勢いや上るさま(動き)はすさまじい。うなぎに因んで、想定や思惑を超える速さや動きで、株価、評価、人気、気温、物価、頻度・・・などがみるみる上昇したり、増加するさま、をいう。
天王山竹寺(埼玉県飯能市南) 瀧尾神社内三島神社(京都市東山区本町)–絵馬
以上51句
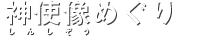

















































拝殿前#-1024x479.jpg)
