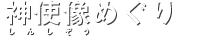Ⅰ 「だいこくさま」 大黒天と大国主命との習合 大黒天は、➀ 元はマハーカーラというインドのヒンドゥーの神で破壊神ともいわれる神でしたが、仏教に取り入れられ、➁ 中国に入って厨房に祀られるようになり、 […]
福田博通
「ゑびす」さま と 鯛+
記紀の三神がえびす神になる 七福神の中では唯一の日本の神です。「えびす・恵比寿」さまと呼ばれる神様は三神あります。➀蛭子(ヒルコ)神、➁少彦名(すくなひこな)神、③事代主(ことしろぬし)神の三神で、い […]
能(謡曲)と神使 後編 ⑤`~⑧+
能(謡曲)と神使 後編 ⑤~⑧ ⑤ 謡曲「賀茂」と 子持ち夫婦猿 ⑥ 謡曲「三輪」と 蛇 ⑦ 猿楽「三番叟」と 猿 ⑧ 狂言「蝸牛」と かたつむり 文中のすべての写真はクリックすると拡大写真になります […]
能(謡曲) と 神使 前編 ①~④+
能(謡曲) と 神使 能(謡曲)の演目や曲目は多数あります。そして、それらの演目の題材とされているものは、全国各地の風俗、習慣、伝承、和歌、記紀、風土記、物語、歴史、仏教説話、仏教の大乗などなどと多種 […]
烏団扇(からすうちわ)と 鵺(ぬゑ)+
烏団扇(からすうちわ)と 鵺(ぬゑ) 東京・府中市の大國魂神社 のすもも祭で頒布される烏団扇(からすうちわ)の烏(からす)は、闇夜(やみよ)の烏で姿が見えない烏です。 鵺(ぬゑ)は、夜の暗闇(くら […]
東京近辺の動物のオブジェ+
東京近辺の 動物のオブジェ 東京近辺の街なかにはたくさんの動物像があります。この稿では「動物のオブジェ・パブリックアート」をご紹介させていただきます。前稿(別稿)の「東京近辺のモニュメント(記念碑・シ […]
白鷺(しらさぎ)伝説・・・三題+
白鷺(しらさぎ)伝説・・・三題 白鷺(しらさぎ)は全国各地で見られる優美な鳥です。地名をはじめ様々なもの・ところに名づけられています。この稿では、「白鷺伝説」が残る、以下の三題を取り上げました。 Ⅰ […]
多摩川の河童と浦安の河童+
全国各地に河童(かっぱ)伝説があります。河童は、川や沼などの水辺に棲む妖怪の類で、馬などを水中に引き込んだりしますが、どこか憎めないとろがあり、頭に水をためるお皿があり、きゅうりを好み、捕らえても放し […]
三本足の烏を持つ「日天」と兎を持つ「月天」+
三本足の烏を持つ「日天」と兎を持つ「月天」 密教の守護神の十二天の中に、日天子(にってんし・日天)と月天子(がってんし・月天)がおられ、「三本足の烏」「兎」を持つ像容も
東京近辺のモニュメントの動物像+
東京近辺の モニュメント(記念碑やシンボル)の動物像 今回は、寺や神社の境内を離れて、東京周辺で出合った街中(まちなか)や街頭の「モニュメントの動物像」を見てみました。
弘法大師と犬 高野山開創伝承+
弘法大師と犬 高野山開創伝承 真言密教の奥義を極めた空海(弘法大師)は、帰国時に唐の浜辺から「真言密教の修行と普及に最適な地に留まれ」と三鈷杵(さんこしょ)を空中に投げました。帰国後、空海は「その三 […]
自分の守護神、一代守本尊+
生れ年の干支による守護神、一代守本尊 1 一代守本尊(いちだいまもりほんぞん)とは 人はだれも、生まれた時から死ぬまでの一生を通して守ってくださる守護神が決められています。守護神は、
重いものを載せたり担いだり+
重いものを載せたり担いだりり 神社や寺の境内には燈籠や石碑、手水鉢、大香炉などがあります。これらの重いものを、台座や脚として、動物、力士、鬼、唐人(唐子)などが、背に載せたり担(かつ)いだりしているの […]
寺の境内の「ゆるキャラ系」+
寺の境内の「ゆるキャラ系」 「ゆるキャラ(ゆるいキャラクター)」とは、地域・町おこしのイベントやキャンペーンのマスコットキャラクター(ぬいぐるみ)などを指すのが一般的です。本来の語源とは異なりますが、 […]
うさぎ うさぎ うさぎ ・・・+
うさぎ うさぎ うさぎ ・・・ うさぎ(兎)は、人に直接危害を及ぼさないうえ、人里近くにも棲息していたことなどから、古来、 身近で親しまれた動物でした。食用や防寒用毛皮ともされました。
ザクロ(吉祥果)を持つインドの女神+
ザクロ(吉祥果)を持つインドの女神・・・孔雀明王と鬼子母神 インドの女神で、梵名マハーマーユーリーと呼ばれる孔雀明王や、梵名ハーリティー=訶梨帝母(カリテイモ)とよばれる鬼子母(きしも)神は「吉祥果」 […]
神使になった いのしし・猪+
神使になった いのしし・猪 2019年の干支は己亥(つちのとい)で、いのしし・イノシシ・猪 年です。「狛犬の杜*別館」HP内の「神使の舘」から、「猪」の項を再編集してここに掲載しました。「神使になった […]
稲荷社の「正一位」と 狐の「命婦」+
稲荷社の「正一位」と 狐の「命婦」 「お稲荷さん」といえば、朱色の鳥居、「正一位稲荷大明神」の幟、狐の石像が、すぐに思い浮かびます。稲荷社は3万社を越すといわれ全国どこにでもあります。
神仏を載せる動物たち+
神仏を載せる動物たち 神仏の像を載せている動物たちがいます。いずれも、特定の神仏それぞれに決まった動物が載せています。これら神仏を載せる動物を私は神使像めぐりの視点から神仏の神使、お使い、眷属、守護神 […]
「ことわざ」と「神使像」のコラボ+
「ことわざ」と「神使像」のコラボ 前門の虎、後門の狼 日常よく使われる、ことわざ・故事成語・慣用句・四字熟語の中には、動物が入っている語句がたくさんあります。
鹿(シカ)も鹿島立ち+
鹿(シカ)も鹿島立ち 鹿島神宮の祭神、武甕槌命(タケミカヅチノミコト)は、 奈良の春日大社の祭神として勧請(神仏の霊を移し祀ること)されました。その際 、命は、常陸(茨城県)の鹿島から 白鹿に乗って出 […]
養蚕の神々 (金色姫伝説)+
養蚕の記憶 はじめに 神使像めぐりで神社仏閣を訪ねていると、 境内などで、かつて、養蚕が≪農家の人々の生活そのものだった≫ことを 物語るようなさまざまな痕跡(遺跡)に出合います。
縁日に奉納された神使+
縁日に奉納された神使 神使(お使い)には必ず主筋に当る神(主神)が在り、 神使像は通常その主神(≒祭神)の近くに奉納されます。 主神は神仏いずれの場合もありますが、神使像の中には「主神の縁日」にこ […]
日光東照宮 14の動物物語 下 10~14話+
日光東照宮 14の動物物語の 「上」「中」に引き続き「下」 をご覧ください。 日光東照宮 14の動物物語 下 10~14話 10 唐門–屋根上の龍とツツガ( […]
日光東照宮 14の動物物語 中 5~9話+
日光東照宮 14の動物物語の「上」に引き続き 「中」 をご覧ください。 日光東照宮 14の動物物語 中 5~9話 5 神厩–馬を守り、世話をする猿 6 御水舎–飛 […]
日光東照宮 14の動物物語 上 1~4話+
日光東照宮 14の動物物語 日光東照宮は 元和3年(1617)徳川初代将軍徳川家康公をご祭神(日光山東照大権現)としておまつりした社です。現在の社殿群は、
碓氷峠 八咫烏と吾嬬者耶(あづまはや)+
ちょうどひと月前に、碓氷峠(うすいとうげ)でバスの転落事故があったばかりです。 碓氷峠は、 日本武尊(やまとたけるのみこと)が八咫烏(やたがらす)に導かれて
国難に馳せ参じた神使—太平記+
国難に馳せ参じた神使-太平記 太平記第39巻に「蒙古襲来の項」があります。 日本の国難に際して、 日本中のすべての神霊と共に 「社々の仕者」も蒙古軍打倒に馳せ参じ、 強烈な台風を起こして […]
扇を持つ猿、恩返しした猿、論語を読む猿+
平成28年(2016)、申年に因んで、 猿の話題をお送りします。 「扇を持つ猿」、 「恩返しした猿」、 「論語を読む猿」をご覧ください。 写真はクリックで拡大してご覧に